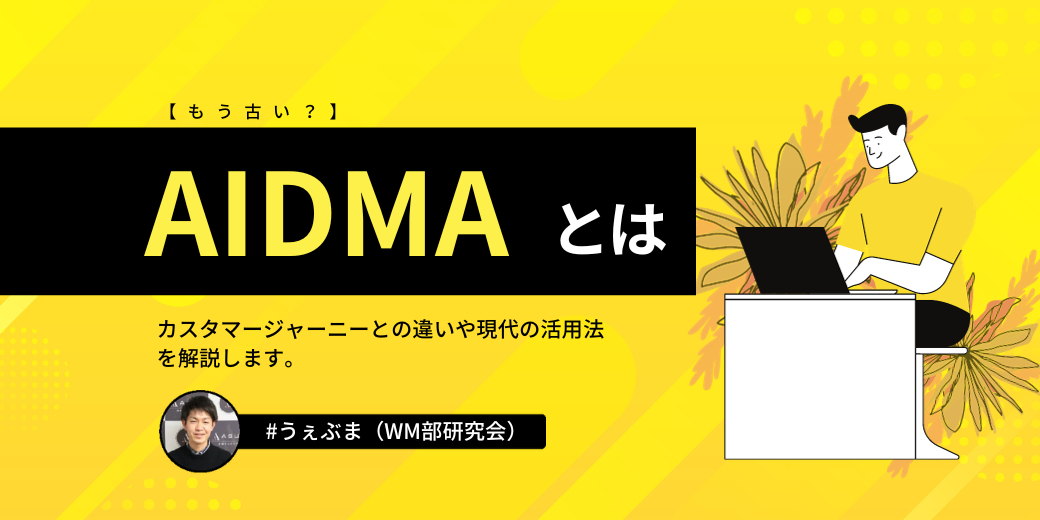
マーケティングは、消費者の購入プロセスを理解しようとするところから始まります。「AIDMA」というマーケティングモデルは、消費者の行動を理解しやすくするため発案されました。本記事では、「AIDMA」の定義から、Webマーケティングでの活用法を探ります。また、カスタマージャーニーとの違いや、AIDMAの現代的な意義についても考察します。消費者の心理を理解し、効果的なマーケティング施策を立てるための基礎知識として、AIDMAの概念は今もなお有効です。それでは、順にみていきましょう。
目次
AIDMAとは何か
AIDMAは、1920年代のアメリカで提唱された消費者の購入プロセスを表す伝統的なモデルの一つです。このモデルは、消費者が商品やサービスに関する情報を得る段階から購入に至るまでの心理の動きを5つのステップに分けて表現しています。
具体的には、「Attention(注意)」、「Interest(興味)」、「Desire(欲求)」、「Memory(記憶)」、「Action(行動)」の頭文字を取ってAIDMAと名付けられました。歴史のあるモデルですが、現代でもこのモデルを理解することで、消費者の購入プロセスをより深く把握し、効果的なWebマーケティング施策を計画することができます。
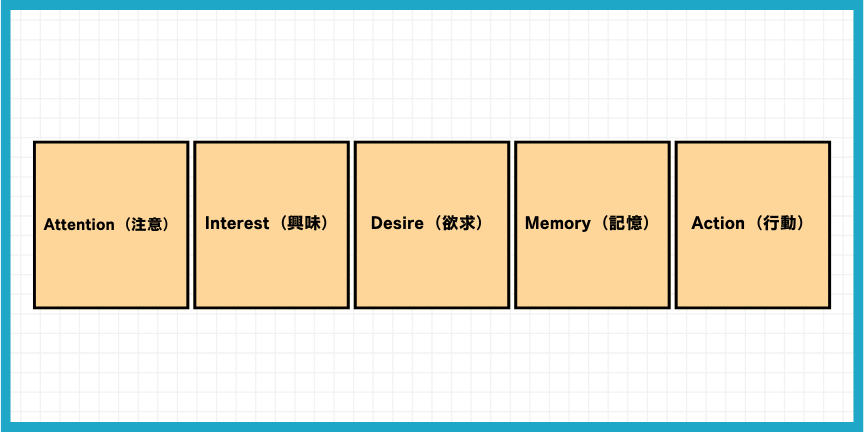
AIDMAとカスタマージャーニーの違い
AIDMAは、消費者の購入プロセスを簡潔な5つのステップで表現していますが、カスタマージャーニーはより詳細かつ複雑なプロセスを考慮できる点が異なります。一般的にカスタマージャーニーは、消費者がブランドや商品との接触から購入、さらには再購入や口コミ発信に至るまでの一連の顧客体験をマッピングするものです。一方、AIDMAは主に購入前のプロセスに焦点を当てています。両者の最大の違いは、カスタマージャーニーがより長期的な関係を考慮に入れている点にあります。
例えば、新しいスマートフォンが市場に登場したとき、消費者はまず広告や店頭での展示を通じてその存在に注意を向けます(Attention)。次に、製品の特徴や機能に関心を持ち始め(Interest)、そのスマートフォンを欲しいと感じるようになります(Desire)。その後、製品名やブランドを記憶し(Memory)、最終的に購入に至る(Action)という流れです。
一方で、カスタマージャーニーは、消費者がブランドや商品に最初に触れる瞬間から始まり、購入後に至るまでを包括的に捉えます。例えば、スマートフォンの購入を考える消費者が、最初に製品レビューをオンラインで検索し、SNSでの評判をチェックし、店舗で実機を試してみるといった一連の行動を取ることが挙げられます。購入後も、製品の使い方を学ぶためのチュートリアルを見たり、使用感をSNSで共有したり、アフターサービスを利用するなど、さまざまな顧客体験を通して製品と関わります。これら全てがカスタマージャーニーに含まれ、ブランドとの長期的な関係構築やロイヤリティの形成に寄与します。
つまり、AIDMAは購入決定に至るまでの心理的プロセスをシンプルに表現しているのに対し、カスタマージャーニーは購入前後の顧客体験を総合的に捉え、より深い顧客理解とエンゲージメントの機会を提供するモデルです。
AIDMAの活用方法
AIDMAモデルを効果的に活用するためには、各ステップに合わせた具体的な施策を考えることが重要です。具体例として、新しいスポーツドリンクの市場参入を考えてみましょう。
まず「Attention(注意)」の段階では、目を引く広告やキャッチーなコンテンツを展開し、消費者の注意を引きつける必要があります。Web広告やSNSの投稿を通じて、ブランドや商品の存在を知らせることが目的となります。
ここでは、インフルエンサーやアスリートを起用した動画広告を作成し、YouTubeやInstagramで配信することが考えられます。また、街中のOOH広告で目を引くビジュアルを展開し、通行人の注意を惹きます。
「Interest(興味)」の段階では、消費者が興味を持った商品やサービスに関する詳細情報を提供することが求められます。FAQや商品の特徴を強調したコンテンツ、動画などを制作し、消費者の疑問を解消することで、興味を深めるサポートを行います。
先ほどの例だと、スポーツドリンクの栄養成分や、体に与える効果に関する詳細な情報をブランドのウェブサイトやブログ記事で提供することが挙げられます。さらに、製品のレビュー動画や使い方を紹介するチュートリアルを公開して、消費者の興味を具体的な情報で支えます。
「Desire(欲求)」の段階では、消費者が商品やサービスを欲しいと感じるような情報やプロモーションを提供します。限定オファーや割引情報、顧客の声などを活用して、購入意欲を高める施策を考えることができます。
スポーツドリンクの例での「Desire(欲求)」施策としては、新製品の発売を記念して期間限定の割引キャンペーンを実施することが挙げられます。また、既に製品を試した人々のポジティブな口コミや、実際にスポーツをしている最中に製品を使用している写真をSNSで共有してもらえれば、他の消費者の購入意欲を刺激することもできます。
「Memory(記憶)」と「Action(行動)」の段階では、リマインダーやフォローアップのメール、リマーケティング広告などを活用して、消費者の記憶に残り、購入につなげる取り組みを行います。
さらに、メールマーケティングを活用して、製品に関する情報やオファーを定期的に送信し、消費者の記憶に製品を定着させることも考えられます。またリマーケティング広告を用いて、一度ウェブサイトを訪れたが購入に至らなかった消費者に対し、SNSや検索エンジン上で製品の広告を再表示し、購入へと導く施策も有効です。
AIDMAはもう古い?
AIDMAは、長らくマーケティングの基本的なフレームワークとして広く認知されてきました。しかし、デジタル技術の進化や消費者の購入行動の変化により、新しいモデルや理論が次々と登場しています。特に、デジタル環境下での消費者の行動は複雑化しており、一つのモデルだけで捉えるのは難しくなってきました。
しかし、コロナ禍を経ても、対面でのコミュニケーションの価値が無くならないことは多くの人が実感しており、店舗ビジネスの有用性は未だ健在です。このような流れも作用して、AIDMAの基本的な考え方は現代のマーケティングにおいても有効であると考えられます。多くの企業やマーケターは、新しいモデルや理論と併用しながら、AIDMAを参考にして施策を計画しています。AIDMAは、消費者の購入プロセスの基本的な流れを理解するためのツールとして、今後もその価値を保ち続けるでしょう。
AIDMA、どう使うのか
現代のWebマーケティングの環境では、消費者との接点が多様化し、購入行動も変化しています。この変化を捉えたモデルとして、AISASが登場しました。AISASは、「Attention(注意)」、「Interest(興味)」、「Search(検索)」、「Action(行動)」、「Share(共有)」の頭文字を取っており、特にデジタル環境下での消費者の行動を反映しています。
AIDMAとAISASを組み合わせて考えることで、現代の消費者の購入プロセスをより網羅的に捉えることができます。例えば、AISASの「Search(検索)」は、消費者が興味を持った商品やサービスについて、自ら情報を検索する行動を示しています。この行動を捉えることで、検索エンジン最適化や検索広告の施策を強化することが考えられます。また、「Share(共有)」は、消費者が自らの経験や意見をSNSなどで共有する行動を示しています。この行動を活用することで、口コミやレビューを通じたブランドの信頼性を高める施策を展開することができます。
AIDMAとAISASを併用することで、現代のWebマーケティング環境において、消費者の購入プロセスを多角的に捉え、効果的な施策を計画することができます。
売り上げを増やすためのWeb広告成功事例集
- CVは付くものの成約に繋がらない
- 今の代理店に不満がある
- 専任担当者がおらず知見・時間が無い
- そもそも広告で成果が出ない

上記のようなお悩みを持った方へ
すぐに役立つASUEの広告改善事例を紹介します!
この記事を書いた人
田中祐晴
旧Twitterリスティング広告・SNS広告の運用5年目
BtoBのリード獲得をメインとした領域の運用型広告コンサルを担当。
成約までを考えた広告設計・改善で伴走支援いたします。






