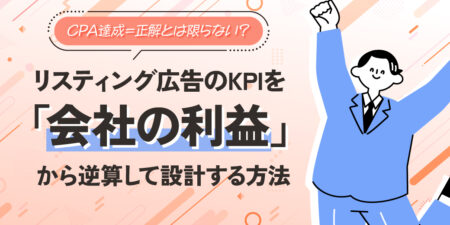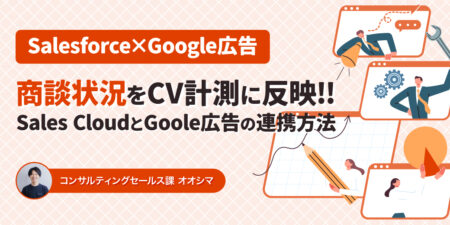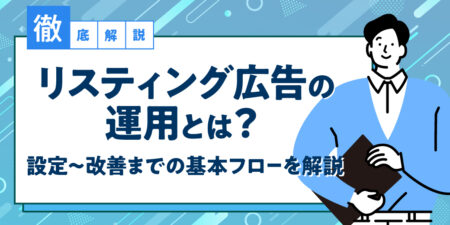こんにちは、ASUEのミヤタです!
さて、前回のASUE通信では「ミヤタ画伯のわかりやすいLP講座 ステップ1『内容を見てもらおう』」と題しまして、広告のランディングページの見た目(レイアウト等)を最低限整えて見やすくしましょう!というお話をしました。
しかし、どれだけ見てもらえても肝心な内容がユーザーに響かなければ、アクションしてもらえません。
今回はステップ2として、商材の良さをきちんとユーザーへ伝えよう!というテーマでお話をしたいと思います!

(ミヤタ画伯って。。。( ˘ω˘)スヤァ)
正しいタイトルは、あなたの広告は大丈夫??最低限確認したいランディングページの3つのステップ STEP 1です!

目次
はじめに――前回のおさらい「内容を見てもらおう」

まずは前回の記事のおさらいです。下記のまとめをがんばって描きました(`・ω・´)
流行りのグラレコってやつです!!!



(LPだけじゃなくてこの図も見やすくしてほしかった。。。( ˘ω˘)スヤァ)
テキストでまとめるとこんな感じです!
内容を見てもらうためのチェックポイント
- テキストびっしりはNG
- ユーザーの閲覧環境を考える
- 商材はわかりやすく明記する
- 専門用語には気をつける
- 欲しい情報は見つけやすく整理する
- 読み込み速度に注意する

以上がページを見てもらうためのスタート地点でしたね!
内容に目を通してもらえるような状態ができたら、次は中身のコンテンツ内容をしっかり伝えたいですよね。
ステップ2では、伝え方に関する最低限の基本的なポイントをチェックしていきます!
ステップ.1 良さをユーザーに届けよう

「商材の良さをきちんと伝える」ための中身(コンテンツ)は、正直もっとも重要で難易度の高い部分です!

そうですね。コンテンツ内容の良し悪しは一概に言えないです。
現役で広告の運用やサイトの制作を行っているような人たちも自社にあった正解を手探りしていることも多いんです…!

すでに自社のターゲットニーズにあったコンテンツの作り方や方向性が見えている場合はそれが正解だと思いますが、今回のステップでは、初めて広告をやってみよう!と思ったときによく起こる、コンテンツの「伝え方の問題」を改善していきたいと思います。

ターゲットは間違っていないのに、良さが伝わらない、アクションする必要がないと思われてしまうようなランディングページには、伝え方に問題がある場合が多いです。
よく起こる問題を大きく以下3つにわけてみました。
- 伝え方が足りない
- 伝え方が弱い
- 伝え方が主観的
順番に見ていきましょう!
伝え方が足りない

良さを伝えるためのコンテンツがそもそも不足していたり、中身の情報量が乏しい状態になっているページやサイトを見たことはありませんか。

情報これだけ・・・!!?って思っちゃうときですね。
例としてこんなLPを用意しました!


(スグネレールマクラ。。。。( ˘ω˘)スヤァ)
値段と商品名、あとは枕のページなんだな、くらいしかわからないのに、この内容で購入フォームを入力するのはちょっと…。

「スグネレールマクラ!?あの有名な!?」くらい市場に浸透しているメジャーな商品ならいけるかもしれませんね!
そうでなければ、自分にとってどんなメリットがあるのかイメージできないサイトで、ものを買ったりサービスを受けようと思うユーザーはほとんどいません。

今回の例のような「30,000円の枕」など相場と比べたとき高く感じる商品や、車や住宅のようにそもそも手を出しづらい価格帯の商材の場合は、特に気をつけたいポイントですね。

このケースは、誰のためのページで、何をしてほしいのか、をあまりイメージできていないときに起こりがちです。
どんな流れでゴールまでたどり着くのかの道のりを考えながらページをつくるようにすると、必要なコンテンツを考えやすくなると思います。
最低限あった方がいい内容の例
- どんな商品なのか
- どんな特徴・強みがあるのか
- どんな人/シーンにおすすめなのか
- 利用することで得られる効果や変化 ……など

膨大すぎる情報は間違えると前回のステップ1のような「見たくない!」になるため注意が必要ですが、情報量が少ないと「やってみたい!」「買ってみたい!」と思ってもらうのは難しくなり、ユーザーのアクションに繋がりにくくなってしまいます。
最低限、ユーザーが商品についてイメージできるような情報量は伝えることが大切ですね。

情報が少ない不親切なページにならないように、気をつけたいです。
伝え方が弱い

よっぽどの独占市場でないかぎり、ネットで探せば同じような商品やサービスは出てくるので、複数の商品やサービスを比較検討しているユーザーは多いです。
他社と比べたときに今ひとつ物足りなく感じたり、明らかに負けているようなアピールポイントをコンテンツに置いてしまっていないでしょうか。

今回は、ほぼ同じようなラーメンを出すA社、B社、C社を例として用意してみました!
それぞれの特徴
- A社・B社:平均的な価格。美味しくてそれなりに人気が高い。
- C社:とても安くて美味しい大人気ラーメン。


A社のように、他社のほうがもっと良いものを提供してくれそうと思われると、比較検討で負けてアクションしてもらえない可能性は高くなります。
このケースは自社の商品やサービスの立ち位置が見えていないときに起こりがちです。

広告を始める前にちゃんと競合分析をしていても、他社の状況は広告を配信したあとも改めて注意したいですね。
広告の運用途中で、「最近コンバージョン数がすごく減ってる……」と思ったら、他社がサイトのリニューアルや新たなキャンペーンを始めていたというのもよくあります…!
さて、A社と同じようなスペックの商材を扱うB社はこんな風に自社商材の強みを押し出しています。


全然内容が違いますね。

伝え方が弱いと言っても、無理矢理に他社より強く見せる必要はないんですよね。
他社と比べて明らかに負けている土俵での真っ向勝負は、逆に挑まないことが勝機を見出すポイントです。
「戦わずして勝ちを得るのは、良将の成すところである。」(`・ω・´)

もしも「負けている土俵での真っ向勝負」をしていた場合は、以下を工夫するといいと思います。
- 競合とは別の土俵でアピールするポイントを考える
- 正面から挑まず、見せ方・言い方を工夫する
アピールポイントとして使える例
- 価格
- 量
- ブランド
- 機能
- スピード
- サービスの質
- 手軽さ
- バリエーション
- オプション ……など
見せ方の工夫例
- 対応エリアが狭い → 地域密着
- 事業規模が小さい → 少数精鋭
- 属人的でマニュアル化されていない → 臨機応変な対応
- 品揃えが悪い → 良いものだけを厳選
- 値段が高い → 成分に妥協がない
- 納期が遅い → 丁寧に仕上げている
- 数が少ない → 希少性が高く人と被らない ……など

他社と比べて強みになりそうなものがあれば、積極的にアピールポイントへ加えたいですね。
また、他社と差別化できるようなポイントが見つからない場合は、商品のポジショニングを修正してターゲットを変えたり、新たにアピールポイントを作ってしまうのもありだと思います。

上にあげた例のように、同じ内容でも、言い方や見せ方を工夫してみることもおすすめです!
言い方を変えたり、"あえてそうあるもの"として納得できる理由が説明できれば、弱みに見えたものが強みになることもありえるので、面白いですよね。

アピールポイントになるかどうかの基準は、ユーザーが何を価値として評価するか、という部分です!
今回のラーメンの例で言うと、「どんなとき食べる」「どんな人が食べる」「どうして食べる」といったユーザーのストーリーを考えられると、自社商品、サービスの強みを想像しやすくなるかもしれません。

独自の魅力ある伝え方ができるよう、自社と競合のページをチェックしてみましょう!
伝え方が主観的

買い手側と売り手側の視点のズレによってたびたび起こるのがこの状況……


お知らせやSNSの更新など自分が伝えたい情報を入れること自体は、一概に悪いことではありません。
書いてあってもいいけど、「ユーザーにとっては優先順位のあまり高くないコンテンツ」であることが多いので、ユーザーが欲しい情報の優先順位を考えてコンテンツは配置するといいですね。

自分が押し出したいところばかりだと、ユーザーにメリットを感じてもらえないばかりか、不愉快を与えてしまう可能性もあります。
その情報はユーザーにとって役立つのか、知りたいことなのかどうか、ユーザーの気持ちを優先して伝える内容を考えられるといいと思います。

また、ユーザーが置いてけぼりになってしまう伝え方には、次のようなケースもあります。


あまりに都合の良いことばかりだと、本当かな……?と疑いたくなったり、不安になったりしますよね。

(ちょっと気持ちわかる……( ˘ω˘)スヤァ)
売り手側が一方的にいいことばっかりを言っていると、自慢話っぽく見えて胡散臭い……と感じるかもしれません。

ネット上では、実際に見たり、触ったりできるわけではないため、安心感は重要な指標になってくるケースが多いです。
高額な商材や身体に影響するような商材の場合は特に慎重に検討したいもののため、より丁寧に伝えることを意識したいですね。

このようなユーザーの不安感を減らす伝え方の例としては、下記のような客観的に見れるコンテンツがおすすめです。
ユーザーの不安を軽減するコンテンツの例
- 事例紹介
- 口コミ
- お客様の声
- よくある質問
- つくり手や売り手、スタッフの顔が分かるような写真

実際の顧客や現場のスタッフに協力してもらう必要があるため手間はかかりますが、企業の主観的な視点よりはるかに効果的です。

同じ内容でも誰が発信してる情報なのかがすごく重要だったりしますよね。
他の人がどう感じたかがわかるコンテンツや、誠実さや親しみを感じるようなコンテンツは安心感に繋がりやすいです。

そうですね。
解消するべきユーザーの不安要素がどこにあるのか見極めることも重要なので、SNSやお悩み掲示板、アンケート調査などで、ユーザーの声を収集するのもおすすめです!

安心感が伝わるかどうかは、アクションを起こしてもらえるかの分かれ目なることも多いため、怠らないようにしたいですね!
「ステップ2:良さをユーザーに届けよう」のまとめ

コンテンツ内容は一概に正解があるわけではありませんが、大切なのは「ユーザー自身やユーザーのニーズをどれだけイメージできるか」「汲み取ることができるか」ということです。
自身の商品やサービスをどんなひとに利用してほしいのか、誰に伝えたいのかをしっかり定めて、ターゲットをイメージしてコンテンツや伝え方を考えられるといいですね。

「ユーザーのよき理解者」になれるよう心掛けたいですね!

ということで、「良さをユーザーに伝えるためのポイント」を紹介しました!
今回の内容も、力作グラレコにしてみます!!!


だからちゃんとユーザーのこと考えてよ!!!!!
(全然成長しないなこの人……)
「良さをユーザーに届けよう」のまとめ
- 誰のためのページなのかを考えて情報を伝える
- 競合をしっかりリサーチして自社の魅力を伝える
- ユーザーの目線で商品の良さや価値を伝える
- 自分以外の人の意見で安心感を伝える
次回予告!「ステップ3:CVをしてもらおう」のご紹介


ステップ3では、きちんとCVをしてもらいやすいようなページ内の導線ができていますか?というお話と、三記事分の最後のまとめまでご紹介します。



近日公開予定なので、併せてご覧くださいませ~!!!
せっかく制作したLP、成果出てますか?
- ブランディング色が強く訴求がおろそかに……
- なんのサービスかがわかりにくい
- ターゲットに刺さりにくいデザインになっている
- CVRが低い・成果に繋がっていない

本資料では、上記のやりがちな失敗を踏まえて
売れるデザインにするための効果的な方法を分かりやすく紹介!
この記事を書いた人
ミヤタアヤノ
2015年秋入社、2020年秋退社した元ASUE社員。好きなものは芋栗カボチャと映画と米津玄師。出社最終日は遅刻した。
今後のミヤタさんのご健闘をASUE一同お祈りしています。