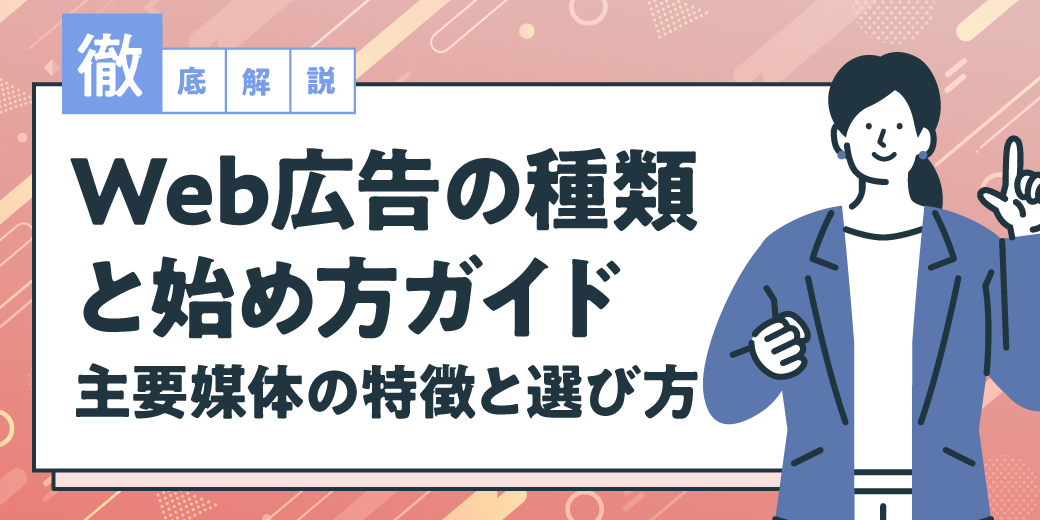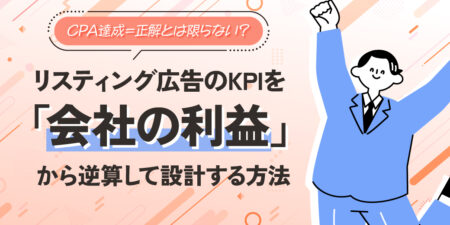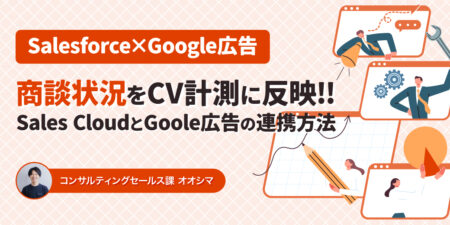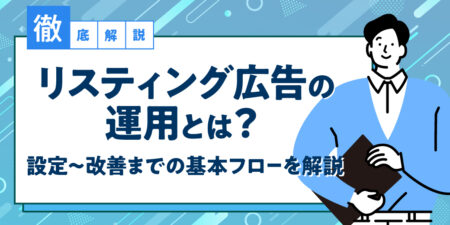インターネット広告市場は年々拡大を続け、2024年には総広告費の半分近くを占めるまでに成長しました。
一方で、実際にWeb広告の運用を始めようとしても「種類が多すぎてわからない」「自社にはどの媒体が合うのか判断できない」と悩む企業が多く見られます。
この記事では主なWeb広告の種類と特徴を整理し、具体的に始める方法を5つのステップで解説します。
目次
Web広告とは
Web広告はインターネット上に掲載される広告の総称であり、GoogleやYahoo!などの検索エンジン、SNS、動画サイト、メールサービスなどさまざまな媒体で配信されています。
新聞やテレビなどのマス広告と比較すると以下の特徴があります。
- 少額から始められる
- 効果測定がしやすく改善が容易
- 顧客を絞った配信に強い
電通による調査では、2024年のインターネット広告費は3兆6,517億円で、日本の総広告費全体の47.6%を占めました。
特に動画広告は8,439億円を突破し、SNS広告も急成長を遂げています。
Web広告は今や、企業のマーケティング戦略に不可欠な存在となりつつあります。
参考:株式会社電通「2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」
Web広告8種類の特徴・メリット・デメリット
ここでは、主な8種類のWeb広告の特徴を見てみましょう。それぞれの特徴を理解し、自社のマーケティング目的に合った広告を選ぶための参考にしてください。
1. リスティング広告(検索連動型広告)
Googleなどの検索エンジンで検索した際に画面の上部や下部に表示されるテキスト広告。
購買意欲が高いユーザーに直接アプローチできます。
主要な媒体にはGoogle広告のほかYahoo!広告やMicrosoft広告があり、想定されるターゲット像などによって配信先を選定すると良いでしょう。
- メリット:ニーズが明確な顕在層に届くため、短期間で成果につながりやすい。
例えば「税理士 無料相談」と検索する人はすでにサービス利用を検討している層であり、コンバージョン率(CVR)が高い傾向にある。 - デメリット:人気のあるキーワードの場合、クリック単価(CPC)が数百円〜数千円に高騰する場合も。特に保険、不動産のような1件あたりの成約単価が高く、かつ広告での競争が激しいジャンルでは顕著。
2. ディスプレイ広告
Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像・動画広告。
視覚的な訴求により、認知拡大やまだ購入の意思が弱い潜在層へのアプローチに有効です。
- メリット:数百万人規模の潜在層にリーチでき、ブランド認知向上に強い。新製品やサービスのローンチ時などに有効。
- デメリット:クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)が低い傾向にあり、直接的な成果につながるまで時間を要しやすい。
3. SNS広告
InstagramやX、FacebookなどのSNSに表示する広告。
SNSごとのユーザー層向けの訴求やブランディングに強みがあります。
- メリット:配信するユーザーを絞るターゲティングを細かく設定できる。
例えば「30代・女性・東京都在住・ヨガに興味あり」など、細かい条件を組み合わせた配信が可能。
動画やカルーセル(複数のコンテンツをスライド形式で切り替えながら表示する手法)など多彩なフォーマットで配信できる。 - デメリット:同じ広告が何度も表示されるとユーザーに飽きられやすく、効果が落ちてくるケースが多いため、定期的なクリエイティブの見直しが必要になる。
4. 動画広告
YouTubeやTikTokなどで配信する動画による広告。
視覚と聴覚に訴えかけるため高い情報伝達力があり、ユーザーの商品理解を深めるのに適しています。
- メリット:商品を使用している様子を見せることで理解度を高められる。
例えば家電や化粧品は「使うとどう変わるか」を直感的に伝えられるため効果的。 - デメリット:制作コストが高くなりやすく、A/Bテストを頻繁に行いづらい。
5. リターゲティング広告
特定のサイトを一度訪問したユーザーに対して表示し、再訪を促す広告。
ECサイトでカートに商品を入れたまま購入していないユーザーへの再アプローチなどが代表例です。
- メリット:一度サイトに訪れたユーザーは検討度が高いため、通常よりCVRが高い傾向がある。
- デメリット:Google検索における規制強化(サードパーティCookieの段階的な廃止)の影響で、今後のターゲティング精度低下に懸念あり。
自社で集めた顧客情報の活用や、会員ログインを活かした仕組みづくりが求められる。
6. ネイティブ広告
記事やニュース、SNSの投稿などに自然に溶け込むように表示される広告。
広告らしさが薄くコンテンツの一部のように見えるため、ユーザーが抵抗感を持ちにくく、スムーズに受け入れられやすいのが特徴です。
- メリット:広告感が弱いためクリックされやすく、ブランドイメージを自然に伝えられる。記事や動画の文脈に沿って訴求できるので理解度も高まりやすい。
- デメリット:記事に混ざって配信されることや、「広告」「PR」の表示がわかりにくいと「騙された」という感覚を持たれるケースもあることから、ユーザーにネガティブな印象を与えるリスクがある。
7. メール広告
メルマガやDMでユーザーに直接届ける広告。
既存顧客や会員へのアプローチに適しており、購入や来店を促すのに有効です。
- メリット:顧客のメールボックスに直接届くため、セグメント配信(顧客の属性や行動に合わせた配信)をすれば高い効果が期待できる。リピート購入やキャンペーン告知に強い。
- デメリット:ほかのメールに埋もれてしまい開封率が低くなりがちで、スパム扱いされるリスクもある。リスト管理や配信設計に手間がかかる。
8. アフィリエイト広告
ブロガーやインフルエンサー(アフィリエイター)に商品を紹介してもらい、購入や資料請求など成果が発生した場合に報酬を支払う広告手法。
成果に応じてコストが発生します。
- メリット:成功報酬型のため無駄な広告費を抑えられる。第三者の紹介による信頼性から購買意欲を高めやすい。
- デメリット:アフィリエイター任せになりやすく、誤解を招く表現や法規制違反のリスクがある。効果的な管理・監視体制が必要。
Web広告8種類の特徴比較表
| 種類 | 主な目的 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| リスティング広告 | 獲得(問い合わせ・購入など) | 顕在層へのアプローチに強い | CPCが高騰するケースがある |
| ディスプレイ広告 | 認知 | 潜在層に広く届く | CTRが低い |
| SNS広告 | 認知・獲得 | 精密なターゲティングが可能 | 媒体ごとの運用知識が必要 |
| 動画広告 | 認知・理解促進 | 高い情報伝達力 | 制作コストが高い |
| リターゲティング広告 | 獲得 | CVRが高い | 規制の影響が懸念 |
| ネイティブ広告 | 認知 | 自然に訴求できる | 「騙された」というネガティブな印象を与えるリスク |
| メール広告 | リピート | 既存顧客に直接届く | 開封率が低い傾向 |
| アフィリエイト広告 | 獲得 | 成果報酬型で無駄なコストが不要 | 管理工数がかかる |
Web広告の運用の流れ:基本的な6つのステップ
Web広告の運用は以下のような計画的なプロセスを踏むことで、限られた予算でも成果の最大化が狙えます。
Web広告運用の運用を開始する前に、全体のフローをきちんと把握しておきましょう!
1. 明確な目標設定
「月間10件の資料請求獲得」「ブランド検索数を半年で2倍にする」など、数値で測れる目標を設定します。
単に「売上を伸ばす」ではなく、どれだけ伸ばしたいのか、そのために達成しなければならないのは何かを掘り下げ、定量的なKPI(指標)に落とし込むことが重要です。
2. ターゲットの明確化
次に、広告を届けたいターゲットを明確にします。
BtoCなら「20代女性・美容に関心あり・Instagramを日常的に使用」、BtoBなら「従業員300人以上の製造業・情報システム関連部署所属の決済権者」といったように、できるだけ具体的に絞ることが大切です。
実際の顧客情報やインタビュー調査をもとにペルソナを作成し、さらに解像度を上げるのも良いでしょう。
これにより、配信する広告媒体選びの精度が大きく向上します。
3. 広告種類の選択
続いては、目的やターゲットに応じた広告種類、媒体の選択です。
例えば、認知を目的とするならディスプレイや動画広告、短期的な獲得を狙うならリスティング広告やリターゲティング広告が有効です。
「Web広告8種類の特徴・メリット・デメリット」の章で紹介した各広告の特徴を参考にしながら、目的に応じた広告を選択しましょう。
予算に余裕がある場合は複数の広告を組み合わせて費用対効果の良い媒体を検証したり、顕在層と潜在層の両方にアプローチしたりすると成果が安定します。
4. アカウント・配信設計
広告種類や媒体を決めたら、次はアカウント構造と配信設計を行いましょう。
入念に広告アカウント構造(キャンペーン・広告グループ・キーワードなど)を設計しておくことで、後の分析・改善のしやすさが大きく変わります。
例えば、商品カテゴリやターゲット属性ごとに広告グループを分ければ、成果を比較・検証しやすくなります。
また、予算配分や入札戦略、配信スケジュールを設計段階で明確にしておくことで、無駄なコストを抑えながら効率的にユーザーへリーチできる可能性が高まるでしょう。
5. クリエイティブ制作
広告文やバナー画像、動画といった、ユーザーとの接点にあたるクリエイティブは、広告の成否を分ける重要な要素です。
広告文は「選んでもらうための根拠」を簡潔に表現することが重要です。
例えば、リスティング広告ならサービスの趣旨や特長のほか、「30日間無料」「資料請求は1分で完了」といった具体的なベネフィットを盛り込みます。
バナーや動画では、テキストだけでは伝えきれないブランドの世界観やサービスの雰囲気を、視覚的に表現することが可能です。
写真やイラスト、色彩を効果的に使い、ユーザーの感情に訴えかけることで、より深いレベルでの興味を喚起します。
6. 分析と改善
Web広告で効果を出すには、配信し始めてからの分析・改善が欠かせません。
CTR、CVR、ROAS(広告費用対効果)などを定期的に確認しましょう。
媒体やキャンペーン、広告グループやキーワードごとに成果を比較し、パフォーマンスが低いものは停止・改善することが大切です。
成功するWeb広告運用の3つのポイント
続いて、広告運用で成功するために欠かせないポイントをまとめました。
広告の成否にはたくさんの要素が絡み合いますが、まずは基礎として以下の3つを押さえておきましょう。
1. 適切な予算設定と配分
Web広告は1日500円程度からでも配信可能ですが、低額すぎると十分なデータが集まらず、改善点を絞りにくくなるため注意が必要です。
予算は「月間CV10件を目指す場合、目標のCV数×1件あたりの獲得コスト(CPA)」といった計算を目安に、適切な落としどころを探りましょう。
初期段階では業界平均やテスト配信を踏まえ、柔軟に調整するのが望ましいでしょう。
テスト配信で効果の高いキャンペーンを見極め、そこに重点的に予算を配分するのが効率的です。
2. ランディングページ(LP)の最適化
広告で興味を引くことができたとしても、クリック後のLPでの体験が悪ければ成果にはつながりません。
広告で高まったユーザーの期待を裏切らないよう、LPでは以下の点を見直しましょう。
- 広告文とLPの訴求が一致しているか
- 申込ボタン(CTA)がわかりやすい位置にあるか
- ページ速度が2.5秒以内か
これらの観点でLPのUIを改善するだけで、CVRが数倍変わるケースも珍しくありません。
Web広告の費用・予算については、以下の記事で詳しく解説しています。
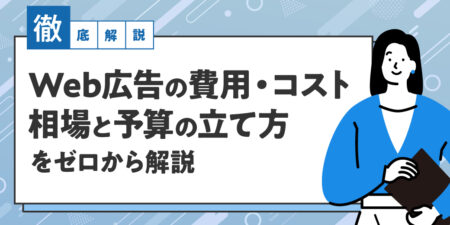
3. データ分析と継続的改善
運用を開始すると、広告の成果が数字になって表れます。
重要なのは、その数字を正しく受け止めて、仮説を立てて改善を繰り返すことです。
Googleアナリティクスや広告管理画面を活用し、ユーザーの行動データを可視化しましょう。
例えば、「広告A経由のユーザーは平均滞在時間が長い」「広告Bは直帰率が高い」といった差を見つけ、原因を特定することで、より的確に改善点を絞り込むことができます。
除外キーワードの設定や配信時間の調整、クリエイティブのマイクロコピーなど、一つひとつは小さな改善でも、その積み重ねが大きな成果につながります。

広告代理店の活用とインハウス(自社)運用の違い
Web広告を始める際に、多くの担当者が悩むのが、代理店に任せるか自社で運用するかという選択です。
両者にメリットとデメリットがあるため、自社の体制や目的に応じて判断しましょう。
1. 広告代理店の活用
Web広告を始めるにあたっては、まずプロである広告代理店への依頼をイメージされる方も多いでしょう。
広告代理店に依頼すると、広告運用の専門家に設計・実行・改善まで実施してもらうことができます。
当然ながら費用はかかりますが、ノウハウのない企業でも早い段階で成果につなげやすいのがポイントです。
- メリット
- 最新の広告トレンドや運用ノウハウをもとにした運用が可能になる
- 広告アカウントの初期設定や入稿作業などの作業を任せられる
- 他社事例や膨大なデータに基づく改善提案を受けられる
- デメリット
- 手数料が発生する(通常は広告費の20%前後)
- 社内に知識が残りにくく、パートナーへの依存度が高まる
- 向いている企業
- 広告予算が一定規模ある(目安:月50万円以上)
- マーケティング部門の人員が限られている
- 早期に成果を出したい
2. インハウス運用
マス広告と違い、ネット環境ひとつあれば配信できるのがWeb広告の魅力。
やり方さえマスターすれば、自社内での運用(インハウス運用)も可能です。
自社内で広告アカウントを管理し、企画から効果測定まで自分たちで行うことになりますが、広告媒体費以外の外注コストがかからないため、長期的な目でノウハウを積み重ねていく体制があるなら検討しても良いでしょう。
- メリット
- 社内にノウハウが蓄積され、長期的な資産になる
- 広告配信の意図や細かな調整を即時に反映できる
- 代理店手数料が不要でコストを抑えられる
- デメリット
- 専門知識を持つ人材が必要
- 運用スキルの習得に時間がかかる
- 他業務と兼務すると成果が安定しにくい
- 向いている企業
- 社内にデジタルマーケティング人材がいる
- 中長期的に広告運用を自社の強みにしたい
- 少額から検証を繰り返し、知見を育てたい
3. ハイブリッド型という選択肢
最近では、広告代理店とインハウスの運用を組み合わせる「ハイブリッド型」も増えています。
例えば、戦略設計や媒体選定、改善アドバイスを代理店に依頼し、日々の広告入稿やレポート作成は社内で行うといった形です。
社内でできることは社内で実施してコストを押さえつつ、難易度が高い部分や特に成果を求められる部分のみをプロに任せたり、インハウスの運用チームが代理店と連携することでノウハウを吸収できたりと、柔軟に成果を追及できるのが魅力です。
自社に最適なWeb広告戦略を見つけよう
Web広告はさまざまな種類があり、それぞれに特徴と強みがあります。
大切なのは「自社の目的・ターゲット・予算」に基づいて正しく選び、改善を繰り返すことです。
この記事で紹介した広告運用のステップやポイントを参考に、最適な方法を見つけてください。
Web広告未経験の場合は、まずはクリエイティブ制作のハードルが低く、成果が見えやすいリスティング広告から始めるのがおすすめです。
そこから少しずつ要領をつかみながら、効果が見えてきたらディスプレイ広告やSNS広告への拡大を検討すると良いでしょう。
判断に迷ったら代理店や専門家に相談するのも有効です。継続的な改善を前提に、自社に合った広告戦略を構築しましょう。
売り上げを増やすためのWeb広告成功事例集
- CVは付くものの成約に繋がらない
- 今の代理店に不満がある
- 専任担当者がおらず知見・時間が無い
- そもそも広告で成果が出ない

上記のようなお悩みを持った方へ
すぐに役立つASUEの広告改善事例を紹介します!
この記事を書いた人
田中祐晴
旧Twitterリスティング広告・SNS広告の運用5年目
BtoBのリード獲得をメインとした領域の運用型広告コンサルを担当。
成約までを考えた広告設計・改善で伴走支援いたします。